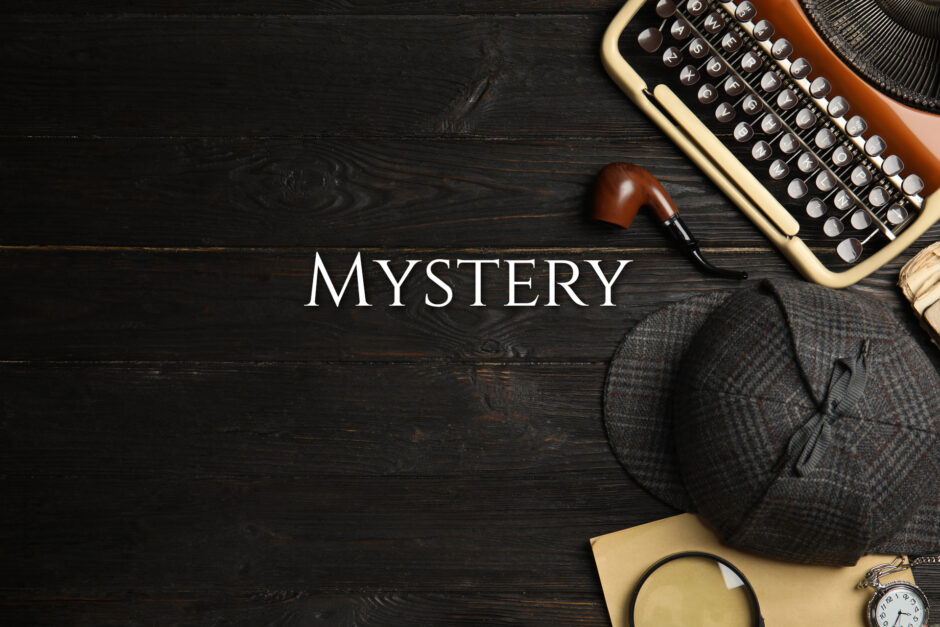当サイトではアフィリエイト広告を使用しています。
ミステリーを書くには、どんな点に注意する必要があるのでしょうか。ミステリーの作り方について、解説本を参考に詳しく解説します。基本から詳しく解説しているので、ラノベなどファンタジーやSFのプロット作りにも応用できる内容です。
そもそも「ミステリー」とは?
ストーリーのジャンルに関する「ミステリー」とは、謎を追っていくタイプのストーリーのことです。
ミステリーの定義について、『書きたい人のためのミステリ入門』という本では、以下のように述べられています。
つまりミステリというのは、〈謎があって、解決するための伏線がきちんと張られていて、その手掛かりを適切に論理的に組み立てれば、唯一無二の真実に辿り着く〉、というタイプの物語だと思ってもらえればいい。
出典:新井久幸『書きたい人のためのミステリ入門』第一章より
つまり基本的には「謎があって」、その「真実に辿り着く」までのストーリーであり、それをしっかりと納得いく形で提示するために「伏線」や「論理的な組み立て」という手法を使っているのがミステリーの特徴というわけです。
基本はこの3つ!ミステリーの種類
ミステリーを書くためには、その「種類」を知っておくことが役立ちます。
ミステリーの分類方法はいくつかありますが、まずは「謎の種類」で分類することが重要です。
ミステリーの謎には以下の3種類がありますが、作品によっては複数のタイプを組み合わせることもあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
犯人は誰?の「フーダニット」(Who Done It)
「フーダニット」とは、誰が犯人か?という謎を解明するタイプのミステリーです。
昔からある定番のミステリーですが、通常は謎の答えが「登場人物のだれか」に絞られるため、意外な展開を作るのに苦労するという面があります。
どうやった?の「ハウダニット」(How Done It)
「ハウダニット」とは、どうやってやったのか?という謎を解明するミステリーです。
例えば主人公には犯人が分かっていて、そのことを証明するために、どうやってやったのか「手口」「トリック」を解き明かしていくミステリーがこれに該当します。
なぜやった?の「ホワイダニット」(Why Done It)
「ホワイダニット」とは、犯人の動機など、なぜやったのか?という謎を解明していくミステリーです。
犯人と手口が分かっていたとしても、「なんでわざわざ、そんなことをしたのか?」という疑問が残るなら、謎になります。
それを追っていくと、思いがけない真実にたどり着く…というような展開のストーリーです。
ミステリーを作るために必要な基礎知識
まずはミステリーを書くために必要な基礎知識を押さえておきましょう。
ストーリーの作り方の基礎として、あらゆるジャンルに重要なことですが、特にミステリーに関係する基礎を3つ、解説します。
「ストーリー クエスチョン」の重要性を知っておく
ストーリー クエスチョンは、ストーリーの「構成」を作るために不可欠な要素です。
ストーリー クエスチョンとは、主人公の目標など、そのストーリーがどこに向かっているのかを示す「中心的な課題」のこと。ストーリーにおける「セントラル クエスチョン」とも呼ばれます。
ストーリークエスチョンがしっかり提示されなければ、読者はそのストーリーを「どう読めばいいのか」が分からなくなり、全体が退屈なものになってしまいます。
ミステリーのストーリー クエスチョンは「謎」です。読者の興味を引くような謎を提示し、それを中心に置いてストーリーを展開することで、一気読みしたくなるような面白いストーリーを作ることができます。
ストーリー クエスチョンについて詳しくは、以下の記事を参照してください。
 ハリウッド式構成の基本「ストーリー・クエスチョン」もしくは「セントラル・クエスチョン」とは?
ハリウッド式構成の基本「ストーリー・クエスチョン」もしくは「セントラル・クエスチョン」とは?
「演繹法」と「帰納法」の使い方を知っておく
ストーリーを考える方法の基本として、「演繹法」と「帰納法」について知っておくことも重要です。
この2つは一般的な「思考方法」の一種で、ストーリーの作り方にあてはめると、以下のようになります。
- 演繹法:冒頭や途中のシーンから「順番に」プロットを考えていく
- 帰納法:結末や途中のシーンから「逆算して」プロットを考えていく
ミステリーを作る上では特に「帰納法」を使うことが重要です。トリックや犯人、事件の全容から逆算してプロットを作ることが多いからです。
演繹法と帰納法について詳しくは、以下の記事を参照してください。
「魔法は一回だけ」の法則を理解する
これもミステリーだけではないストーリー作りの基本法則ですが、「魔法は一回だけ」という点も意識することが重要です。
「魔法は一回だけ」というのは、ありえないような偶然や、ファンタジー設定、奇跡のような出来事は、一つのストーリー内で一つに絞るべきという原則です。
その点は、ハリウッド脚本術の権威ブレイク・スナイダー氏の解説によると、以下のとおりです。
一本の映画で使える《魔法は一回だけ》。鉄則である。UFOに乗って地球にやってきたエイリアンが、吸血鬼にかまれて〈不死身のエイリアン〉になった、なんていうのはナシってこと。
出典:ブレイク・スナイダー著『SAVE THE CAT の法則』菊池淳子訳 Chapter 6 より
例えば妖怪が登場する話に、宇宙人や未来人も同時に登場すると、「魔法」が2つも3つもあることになり、読者の中に「そんなことあるわけない」という気持ちが起きて冷めてしまうのです。
『涼宮ハルヒの憂鬱』というラノベでは、未来人と超能力者と宇宙人などが同時に登場しますが、「それらはすべて涼宮ハルヒが原因で出現している」という一つの魔法に集約されているので、ルール違反ではありません。
ミステリーの場合、そのようなファンタジー設定は関係ないことが多いですが、関連性のない「偶然の出来事」や「奇怪な事件」が多くなると、魔法が増えていくことになります。
どのように気を付ける必要があるのか、詳しくはこのページ内で後述しています。
「伏線」の張り方を知っておく
どんなストーリーにも伏線は重要です。
伏線は、クライマックスを盛り上げたり、期待させたりするための、重要な演出方法でもあります。
ミステリーでは特に、事件の解決方法、謎の解き方についての「説得力」を持たせるために、伏線が重要です。
伏線について詳しくは以下の記事を参照してください。
 伏線とは?それを回収するとは?伏線はストーリーを面白くするのに大切!
伏線とは?それを回収するとは?伏線はストーリーを面白くするのに大切!
ミステリーの作り方・基本の流れとコツ
もちろん作り方は人それぞれですが、ミステリーの基本の作り方について、参考文献を使いながら解説します。
トリックや事件の全容から考える(帰納法)
ミステリー創作の手順としておすすめなのは、トリックや事件の全容から先に考えて、そこにたどり着くためのプロットを作っていく方法。
つまりオチから先に考える「帰納法」です。その点について、小説家・貴志祐介先生は、以下のように述べています。
(前略)いずれもアイデアの根本はトリックで、これがなければ何も始まらない。プロットを作る際も、トリックから逆算して、それが成立するための環境や条件を確定していく手法を採っており、他の作品とはプロセスはまったく異なっている。
出典:貴志祐介『エンタテインメントの作り方』第二章より

冒頭から順に考える「演繹法」だと、無難な展開になりやすく、意外な展開を考えるのが難しくなります。一方の帰納法では、意外性のある「どんでん返し展開」が自然に出来上がることも珍しくありません。
まずは面白いトリックや、印象的なシーン、感動的な動機などを先に考え、そこに持っていくためのストーリー展開や世界観を組み立てていきましょう。
興味を引く謎を考える(ストーリー クエスチョン)
次に興味を引く「謎」を考えます。
謎はミステリーの「ストーリー クエスチョン」であり、読者の興味を引き付けるための軸です。
その謎が興味をそそられる内容でなければ、その後も読者の興味を引き続けるのは難しいでしょう。
その点は、前述の『書きたい人のためのミステリ入門』という本では以下のように述べられています。
(前略)謎が大きく、不可解であればあるほど、読者はその真相を知りたくて、ページをめくることになる。
出典:新井久幸『書きたい人のためのミステリ入門』第一章より
いかに「真相を知りたくて、ページをめくることになる」ような謎を作れるかどうかが、ストーリー全体の面白さに大きく影響するわけです。
「雰囲気の演出」や「見せ方」を大切にする
怖い雰囲気や、ドキドキするような展開、かっこよく見せる演出などで「飾り付け」をすることも、ミステリーには重要です。
その点が、『ミステリーの書き方』という本で以下のように解説されています。
(前略)トリックも論理も、それ単体では脆弱であり、無味乾燥なものです。トリックや論理の周囲には、それらが世界で一番の美人――とんでもなく神秘的――に見えるよう、過剰なほどの装飾を施す義務が作家にはあるのです。
出典:『ミステリーの書き方』(日本推理作家協会)――『本格推理小説におけるプロットの構築』二階堂黎人 より
つまり、謎とその解決、トリックの解き明かしなどを、ただ分かりやすく説明するだけでは「無味乾燥」で、大したトリックには感じられないことが多いということですね。
同じトリックでも「雰囲気の演出」や「見せ方」の工夫をするだけで、ものすごいトリックのように見せられるわけです。
謎からオチへのプロットを考える
トリックと謎ができたら、ストーリー構成の基本に従って、プロット全体を考えていきましょう。
伏線を張っていくのはもちろん、起承転結や三幕構成など、ストーリー構成の基本に沿って設計していくことも重要です。
起承転結については、以下の記事で解説しています。
 ストーリーの起承転結とは?それぞれの意味を解説!三幕構成と比較してまとめてみた
ストーリーの起承転結とは?それぞれの意味を解説!三幕構成と比較してまとめてみた
ミステリーで避けるべきNG展開
「こんな展開は、読者を興ざめにさせる」というような、ミステリーで避けるべきNG展開を2つ紹介します。ミステリー以外にも当てはまる点です。
伏線なしの「超展開」
超展開は、ミステリーに限らずどんなストーリーでも避けるべきでしょう。
超展開とは、読者・視聴者の予想を「悪い意味で」裏切り、「そんな解決方法はナシだろ」などと思わせてしまう、とんでもない展開のことです。
超展開は多くの場合、解決方法の「伏線」が無いか、あっても読者・視聴者の記憶に残っていない場合に発生します。
伏線をうまく張ることで、超展開を避けることが可能です。伏線について詳しくは、以下の記事を参照してください。
 伏線とは?それを回収するとは?伏線はストーリーを面白くするのに大切!
伏線とは?それを回収するとは?伏線はストーリーを面白くするのに大切!
いろいろ盛り込みすぎる「多すぎる魔法」
ミステリーでは「魔法は一回だけ」の法則も守るように注意が必要です。
ミステリーの場合、例えば「ありえない殺人事件」という魔法を使ったなら、それとは何の関係もない「もう一つの奇妙な事件」を起こしてしまうと、魔法の回数が増えてしまいます。
複数の大事件が起こるなら、一つの大きな事件が発端になっているなど、一つの魔法に集約されていることが重要です。
ありふれた内容の事件なら「魔法」に該当しないこともあるので、「事件は一つじゃないといけない」という意味ではありません。
とにかく「すごい事件がいくつも起こりすぎ」「こんな偶然が重なるわけない」と読者がシラケないようにするということです。
ミステリーの作り方でよくある疑問
ミステリーの作り方について、ありがちな疑問を2つ、Q&A形式で解説します。
厳密なルールを守らなきゃいけない?
そもそも「厳密なルール」は存在しません。
ミステリーを書こうと思わない人の理由として、「厳密なルールがあってめんどくさそう」というものがあるでしょう。
確かに『ノックスの十戒』『ヴァン・ダインの二十則』など、ミステリーのルールのようなものが知られているので、そう思うのかもしれません。
しかしこれらは「厳密なルール」ではなく、面白いミステリーを書くための「コツ」を列挙したようなものです。
代表的な『ノックスの十戒』は以下のとおり。
- 犯人は、物語の初期の段階から登場している人物であらねばならぬ。しかしまた、その心の動きが読者に読みとれていたものであってはならぬ。
- 言うまでもないことだが、推理小説に超自然的な魔術を導入すべきでない。
- 秘密の部屋や秘密の通路は、せいぜい一つにとどめておかねばならぬ。
- 現時点までに発見されていない毒物、あるいは、科学上の長々しい説明を必要とする装置を使用すべきでない。
- 中国人を主要な人物にすべきでない。
- 探偵が偶然に助けられるとか、根拠不明の直感が正しかったと判明するなどは避けるべきである。
- 推理小説にあっては、探偵自身が犯行を犯すべきでない。
- 探偵が手掛かりを発見したときは、ただちにこれを読者の検討にふさなければならぬ。
- 探偵の愚鈍な友人、つまりワトソン役の男は、その心に浮かんだ考えを読者に隠してはならぬ。そして彼の知能は、一般読者のそれよりもほんの少し(ほんの少しである)下まわっているべきである。
- 双生児その他、瓜二つといえるほど酷似した人間を登場させるのは、その存在が読者に予知可能の場合を除いて、避けるべきである。
厳密なルールというよりも、「この点に注意しないと、読者はシラケるよ」という警告のような意味合いでしょう。
重要なのは、読者が面白いと感じるか、納得できるかどうかです。そのための「参考」として利用できます。
ミステリーもストーリーの一種ですから、「エンタメとしてのストーリーの基本法則」を守っていれば問題ありません。
ストーリーの基本法則については、前述の「ミステリーで避けるべきNG展開」を参考にしてください。
SF・ファンタジー設定は使えない?
ハウダニットの場合は要注意ですが、フーダニット・ホワイダニットなら問題なく使えます。
前述のノックスの十戒には「超自然的な魔術を導入すべきでない」とありますが、これはハウダニットの謎が関係する場合だけです。
どうやってやったのか?(ハウダニット)という謎に対して、魔法や科学で何でもできる世界だと、無限の可能性があって面白くないからですね。
絶対に無理とは限りませんが、「何が可能で、何が不可能か」をしっかり設定し、「そんなのナシでしょ」と読者に思われないようにする必要があります。
一方、誰がやったのか?(フーダニット)や、なぜやったのか?(ホワイダニット)の謎は、何でもできる世界でも成立します。ラノベのような設定でも十分可能です。
実際、SF・ファンタジー設定を使ったミステリーは、昔からたくさんあります。
ジャンルにとらわれない!いろいろなミステリーの例
ミステリーにもいろいろあることを示す例として、SFミステリーと、日常ミステリーの2種類を紹介します。
SFミステリー「星を継ぐもの」
ミステリー要素のあるSFは沢山ありますが、優秀な本格ミステリーとしても知られるのが『星を継ぐもの』です。
冒頭で大きな謎が提出され、それを解明していくという本格ミステリーであり、本格SFでもある名作。
星野之宣氏によるマンガ版があったり、『映画版 機動戦士 Zガンダム』のサブタイトルになったり、アニメ『不思議の海のナディア』の最終回のタイトルに使われたりと、日本のクリエーターにも色々な意味で影響を与えた作品でもあります。
日常ミステリー「動物のお医者さん」
日常系のストーリーなのにミステリー展開で盛り上げている作品として、漫画『動物のお医者さん』を紹介します。
ミステリーといっても、提示される「謎」は大したことじゃありません。「犬のチョビの毛をむしった犯人は誰か」「イタズラの犯人は誰か」「管理シールを勝手にはがす犯人は誰か」というようなことです。
本来のジャンルとしては「動物もの」「大学もの」ですが、話の展開的にはミステリー要素を多く取り入れているので、いわゆる殺人が登場しない「日常ミステリー」「日常の謎」のジャンルに入れてもいい作品だと思います。
まとめ
ミステリーでは、興味深い謎を考え、その解き明かしをいかに面白く演出するかが重要です。そのために「帰納法」や「伏線の張り方」のコツを知っておくことが役立ちます。
ストーリーの作り方全般に関するコツについては、以下の記事も参照してください。